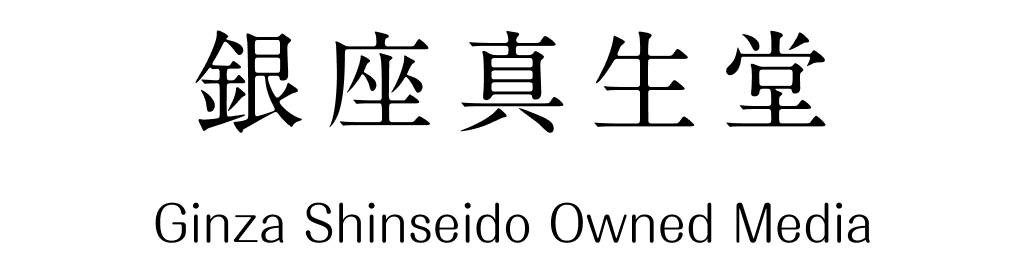七宝(七宝焼)独特の美しさを堪能! 歴史と技法の魅力を紐解く

七宝(七宝焼)は、その独特の美しさと緻密な技法で多くの人を魅了してきました。
本記事では、七宝の美しさを堪能しながら、その歴史と技法に迫ります。
歴史を知ることで美しさの根源を理解することができます。七宝は現代の技術では真似することができない技法の数々が詰まった作品です。
現代では、材料費・人件費・膨大な時間の確保が理由から現実的に明治時代の七宝を再現することは不可能です。
その歴史的背景や、緻密な技法が生み出す色彩豊かな作品の数々を紹介し、その七宝の魅力を知っていただきます。
七宝の奥深い世界へ、一緒に旅を始めましょう。
七宝(七宝焼)の美しさとは
七宝の美しさとは、彩り鮮やかで美しいデザインが特徴的で、独特の輝きを持つ美しい装飾品です。金属製の器や陶器に、釉薬を流し込み、美しい模様やデザインを生み出す七宝は、緻密で精密な技術が必要なため、高い職人技を持つ職人によって製作されています。
また、丈夫で耐久性があり、美しさを長く保つことができるため、贈り物やコレクションとして人気もあります。
七宝は、その美しさから、贈り物やコレクションとしても人気があります。また、七宝の美しさは、年代や地域によっても異なり、それぞれ独自の特徴を持っています。模様や、明治時代の自然物をモチーフにしたデザインなどが代表的なものです。取り扱いにも注意が必要です。
七宝(七宝焼)の美しさを彩る技法
有線七宝
有線七宝とは、銅や銀などの素地に下絵を描き、下絵にしたがって帯状の金属線で色の境目を作り、その中に釉薬をのせ、焼成し、研磨した近代七宝の基本となる技法です。
無線七宝
無線七宝は、有線七宝と同じく植線により模様を描き釉薬をのせるが、その後焼成する前に金属線を取り除き、研磨した技法です。明治13年(1880)濤川惣助によって考案されたと伝えられています。無線七宝によって美しいグラデーションやぼかしができるようになりました。
盛上七宝
盛上七宝とは、研磨の途中で、盛上げようとする部分にのみ釉薬を使い、盛り上げて焼成し、完成させるものです。より立体感を生むために作られた技法です。
省胎七宝
省胎七宝は、主銅の素地に銀線で植線し、透明釉を施し焼成・研磨で仕上げた後、銅の素地を酸で腐食させて取り除き、表面の銀線と釉薬だけを残したものです。
銀線と釉薬の透過効果をねらったもので、完成品はガラス製品のように透き通ります。
しかし、銀線と釉薬だけでできているため、他の七宝に比べて壊れやすいのが欠点です。
明治30年(1897)頃、川出柴太郎によって考案されたといわれています。
透胎七宝
胎の一部を切り透かしにして透明釉を施す、あるいは、銅胎の一部を切り透かしにして透明釉を施し、他の銅素地の部分には通常の七宝を施す技法のことです。
陶胎七宝
陶胎七宝とは、陶器の素地に七宝を施したものです。
磁胎七宝
磁胎七宝とは、磁器の素地に七宝を施したものです。
銀胎七宝
銀張七宝は、銅の素地の表面に銀箔を張り、その上に透明や半透明の釉薬を盛りつけて焼成する技法です。銅の素地を使って、銀の素地を用いた時と同じような効果をねらって考え出されたものです。明治27年(1894)に塚本甚平により考案されたもので、明治35年(1902)頃盛んに作られました。
この8種類の技法によって七宝の美しさが彩られていくのです
七宝の技法について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

七宝(七宝焼)を彩る歴史
現代で超絶技巧と評される七宝は、江戸時代後期に梶常吉(かじつねきち)によって生み出されました。名古屋の骨董品店で店主からオランダ渡りの七宝の皿を譲り受け、そのお皿を割り、どのように制作されているのかを研究したといわれております。その後、梶常吉は五寸ほどの七宝の鉢を完成させます。
七宝の歴史について詳しくしりたい方は、下記の記事をご覧になってください。

まとめ
いかがでしたか。
七宝の美しさについて解説させていただきました。
七宝は歴史とともに技法が進化し、美しさが増しています。超絶技巧と評される七宝は、江戸時代に生み出され、現在まで受け継がれています。
この美しさを多くの人に伝えたいと思い、今回の記事を執筆しました。まだ七宝の美しさや魅力を知れていない方は、ぜひ読んで当店に足を運んでみて下さい。
きっと七宝の魅力に驚くでしょう。