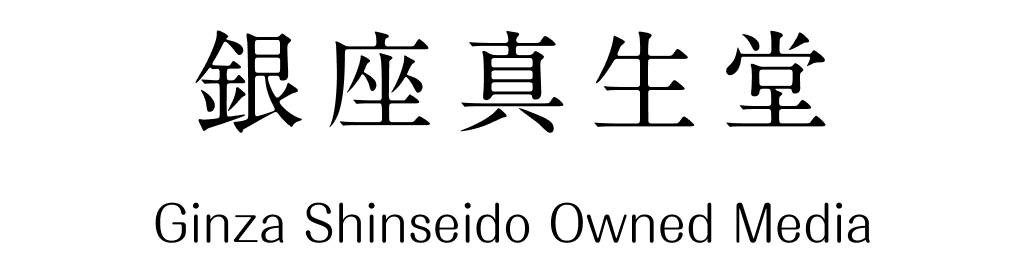明治七宝(七宝焼)とは?歴史・特徴を完全網羅

明治七宝は、日本の代表的な工芸品の一つであり、世界中から愛されています。しかし、その中でも特に注目されているのが明治七宝です。
「明治七宝ってどういうもの?」
「明治七宝ってどんな特徴があるの?」
「明治七宝ってなんで世界的に有名になったのかな?」
などの疑問があると思います。
そこで、今回の記事は、明治時代の七宝について詳しく解説していきます。
明治時代の七宝は黄金時代と呼ばれ、日本の技術が世界的に誇れるものです。
明治の七宝の歴史的背景、特徴を理解することで七宝の魅力が伝わるでしょう。
ぜひ興味のある方は、こちらの記事で学んでみてはいかがでしょうか。
それでは参ります。
七宝(七宝焼)とは
まず、七宝について解説します。
七宝焼(しっぽうやき)は、金属や陶器の表面にガラス質の釉薬を絵の具のように塗り、高温で焼成することによって美しい模様や色彩を表現する日本の伝統工芸技法です。
その名は、もともと中国で生まれた「七宝」という仏教の語から来ており、実際には七つの宝物を意味しますが、美しい色と光沢を持つガラス質の釉薬を用いることから、この名が付けられました。
以下の記事で七宝について詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

明治七宝とは
明治時代には、無線七宝を考案した東京の濤川惣助、有線七宝で日本画の筆致を生かす繊細な七宝を製作した京都の並河靖之など、現代でも有名な作家が活躍した黄金時代です。
ドイツ人のワグネルと共同開発した透明釉薬の技術を用い、七宝の技術は飛躍的に発展し、世界中から日本の七宝は価値を高めました。
そんな黄金時代に作られ、釉薬によって美しい色使いが生まれた七宝が「明治七宝」になります。
明治七宝(七宝焼)の歴史
幕末前夜の天保年間(1830 – 1844年)の頃に、尾張藩士の梶常吉(1803-1883年)オランダ船にあった皿がすべて七宝であったことから歴史は始まります。
名古屋の骨董品店で店主からオランダ渡りの七宝の皿を譲り受け、そのお皿を割り、どのように制作されているのかを研究したといわれております。
その後、日本に七宝文化が根付くことになるのです。そして梶常吉は五寸ほどの七宝の鉢を完成させます。

明治七宝が発展した背景
七宝は、明治時代に政府の指示により外貨を稼ぐ為に制作されました。
外貨を稼ぐ為には外国人に販売し外貨を得るわけですが、良い作品でなければ売れません。当時、名古屋、京都などで多数の七宝工房がありました。それぞれの工房が良い作品を作ることに励み、良きライバルとして技術を高め、時間をかけて丁寧に作り上げました。
その成果もあり、当時の七宝作家は国内外の博覧会などで数多くの賞を受賞しました。

(並河靖之の工房の様子)
明治七宝の特徴
先程も説明したとおり、明治時代の七宝は技術レベルが飛躍的に成長した時期になります。
・釉薬の開発によって、色使いの幅が広がった
・無線七宝の技術によって、グラデーションなど美しい色使いを生まれた
・有線七宝によって細やかで繊細な表現が確立した
・有名作家が生まれ、現代でも作品の価値が高まっている
などの、明治時代に技術の礎が作られ、現代の技術に紡がれています。
七宝(七宝焼)の製作労力は計り知れない





釉薬は水分を含んでいるので金属線の高さまで差した釉薬は焼成すると半分以下まで目減りしてしまいます。

STEP4〜5の作業を何度も繰り返して、やっと線の高さより上になります。




↑ちらの作品(林小伝治の作品)もSTEP1〜7の工程で製作されております。
これだけの細かい図柄に金属線を立て、何度も釉薬を差すのはとても大変な作業であり、途方もない時間を費やして作られたのが分かります。現代では再現不可能です。
七宝(七宝焼)の名工紹介
並河靖之

日本を代表する七宝作家の一人で京都で活躍されました。
近代七宝の原点である有線七宝に拘り、それを極め、緻密で美しい作品を世に残しました。
国内外の博覧会などで数多くの賞を受賞されております。
1896年に東京の濤川惣助と共に帝室技芸員に任命されています。
並河靖之について、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ読んでみてください

濤川惣助

東京を中心に活躍された七宝作家。
濤川惣助は絵画的に図柄を表現する無線技法を発案しました。
濤川惣助によって無線技法で製作された『七宝富嶽図額』は重要文化財に認定されております。
1896年に京都の並河靖之と共に帝室技芸員に任命されています。
林小伝治

尾張を中心に活躍された七宝作家。
外国人に七宝を初めて販売した人物で輸出の先駆けとなりました。
製作技術が高く、並河靖之、濤川惣助と共に緑綬褒章を受章するなど明治の七宝作家を代表する一人です。
安藤重兵衛

尾張、東京を中心に活躍した七宝作家。
安藤重兵衛は研究熱心で西洋のプリカジュールに感銘を受け、川出柴太郎と共に省胎技法を生み出しました。
国内外の博覧会などにも積極的に出品し、数多くの賞を受賞されています。
川出柴太郎

安藤七宝店(安藤重兵衛)の工場長として活躍された七宝作家。
工場長としての役目が忙しかったのか個人の作品は殆ど残されておりません。
僅かに残された作品はどれも素晴らしく、現代アートのような他と違ったユニークな作品も製作されております。
七宝(七宝焼)の技法紹介
有線七宝

有線七宝とは、銅や銀などの素地に下絵を描き、下絵にしたがって帯状の金属線で色の境目を作り、その中に釉薬をのせ、焼成し、研磨した近代七宝の基本となる技法です。
有線七宝に関しては、こちらの記事で詳しく解説しておりますのでぜひ読んでみてください。

無線七宝

無線七宝は、有線七宝と同じく植線により模様を描き釉薬をのせるが、その後焼成する前に金属線を取り除き、研磨した技法です。明治13年(1880)濤川惣助によって考案されたと伝えられています。無線七宝によって美しいグラデーションやぼかしができるようになりました。
無線七宝に関しては、こちらの記事で詳しく解説しておりますのでぜひ読んでみてください。

盛上七宝

盛上七宝とは、研磨の途中で、盛上げようとする部分にのみ釉薬を使い、盛り上げて焼成し、完成させるものです。より立体感を生むために作られた技法です。
省胎七宝

省胎七宝は、主銅の素地に銀線で植線し、透明釉を施し焼成・研磨で仕上げた後、銅の素地を酸で腐食させて取り除き、表面の銀線と釉薬だけを残したものです。
銀線と釉薬の透過効果をねらったもので、完成品はガラス製品のように透き通ります。
明治30年(1897)頃、川出柴太郎によって考案されたといわれています。
透胎七宝

胎の一部を切り透かしにして透明釉を施す、あるいは、銅胎の一部を切り透かしにして透明釉を施し、他の銅素地の部分には通常の七宝を施す技法のことです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、明治七宝について記事を書きました。
明治時代の七宝の特徴として
- 釉薬の開発によって、色使いの幅が広がった
- 無線七宝の技術によって、グラデーションなど美しい色使いを生まれた
- 有線七宝によって細やかで繊細な表現が確立した
- 有名作家が生まれ、現代でも作品の価値が高まっている
などがあります。
明治時代は七宝黄金時代であり、今の技術の礎ができた時代でもあります。
並河靖之や濤川惣助など有名作家が活躍し、世界的な評価も集まっております。
現代では明治時代の七宝の価値が高まり、なかなか手に入らない代物です。
ぜひ、銀座真生堂に足を運んでいただき、明治七宝の良さを感じていただけたらと思います。